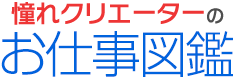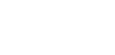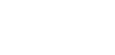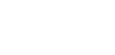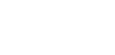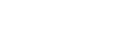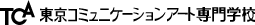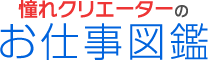照明コンサルタントって、どういう仕事?
ランドマークや建築物のライトアップが盛んに行われるようになっています。光の当て方によって、建造物を幻想的に浮かび上がらせることができるからです。また、飲食店や住居でも光の演出によって空間の表情が変わり、穏やかに過ごせる環境に変化させることが可能です。光には周囲を明るくするだけではなく、人々の暮らしや気持ちを豊かにする力があるわけです。
照明コンサルタントは、照明器具や光に関する知識を生かし、住宅や店舗、事務所などにマッチした照明器具の提案や、照明設計のアドバイスといったコンサルティングを行うのが仕事です。建造物や内装の構造を見て、照明器具を設置する位置を決め、照明の効果的な当て方や、照明器具の選び方、省エネになる照明の方法など、照明に関するさまざまな点をアドバイスしていきます。
照明コンサルタントのなかには、照明器具メーカーで勤務する社員もいます。また、インテリアコーディネーターがキャリアップのために目指すケースもよくあります。
照明コンサルタントに関連する資格として、照明コンサルタントの資格があります。これは社団法人照明学会が主催している資格で、講座を受講することで照明コンサルタントとして認定されます。資格は5年更新で、必ず取得しなければいけないものではありませんが、照明に関するコンサルティングを行ううえでのアピールポイントとなり、説得力アップにつながります。
お仕事完了までの流れ
続いて、照明コンサルタントの仕事内容を見ていきましょう。どのような手順で仕事をしていくのか、依頼から完了までの流れを簡単に解説していきます。
依頼主から要望や不満、トラブルの内容をヒアリング
照明コンサルティングの依頼を受けたら、直接依頼主のもとを訪ねてヒアリングを実施します。日々その空間にいて感じる照明への不満や悩み、疑問を聞きだしていきます。
光の状態を確認する
実際に照明に問題がある建築物や店舗などに足を運び、自身の目で現状を確認します。もし諸事情で直接現場に行けない場合には、図面や写真で確認します。
問題点を洗いだし、原因を説明する
現場の状況を確認したら、なぜ照明に不満を感じているのか問題点を洗いだします。原因がはっきりとわかったら、依頼主に説明します。
改善策の提案
続いて改善策をいくつか提案し、どのように対処すべきかを依頼主に決断してもらいます。予算や改善にかかる期間もあわせて提示します。営業中の店舗や事務所ですぐに改善することが難しければ、長期的な計画も作成します。
これ、どういう意味?
どのような仕事にも、その職業に関わる人たちがよく使う専門用語があります。ここでは、照明コンサルタントが使う業界用語を取り上げます。
「配光」
照明器具からどれくらいの強さの光が、どちらにでているのかを表す言葉です。「あの照明は配光が広い(狭い)」と使用します。
「グレア」
テレビを見ているときに画面に光が映りこみ、映像が見えにくいことがあります。また対向車のヘッドライトに視界を遮られることがあります。こうした良好な見え方を邪魔するものや、まぶしさのことをグレアと呼びます。
- 総合トップ
- クリエーティブトップ
- 憧れクリエーターのお仕事図鑑
- 建築やインテリアの仕事
- 照明コンサルタントのお仕事内容